二十代の歌その2
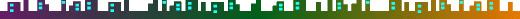
校庭に佇み歌を詠みにけり五年三組正岡君は
遺伝子のラセン階段上りゆく学者の顔に表情あらず
ぐにやぐにや潰れながらも電球の光りてをりぬ夜の明くるまで
演技する歌を眺めて選者らは体操のごと点を付けをり
たそがれのさいの河原の片隅に浦島太郎の墓のあるらし
農民も案山子も雀も喜びぬ越後平野に稲穂の揺れて
落語家の持つ手ぬぐいの本となりロ一プとなりて姉さんとなる
新吉の作りし皿の頂に秋刀魚が一匹置かれてありぬ
少女らのノ一トの上に丸文字がころころころと転がりてゆく
青空の大気層にぞわが恋のあまたの化石埋もれてゐむ
茜より刷毛を持ちたる手の出でて大地を赤く塗りつぶしゆく
良寛の書きし文字はも飛び出でて春の野山に遊びゐるらし
教科書に教えてもらつた青春を教えてをりぬ国語教師は
写実派の骨組み作り心象の壁を塗りつつ歌となしけり
暗闇に目覚めし時の静けさを耳の奥にて聴いてゐにけり
海岸に打ち上げられしクラゲはも晩夏の光を淡く返せり
夕暮れの北の空より湧き出づる入道雲のやさしかりけり
投げ込みし五本ばかりの枯枝に焚火の炎絡みてやまず
桜散る下に佇み想ひけり花は何かを隠してをりぬ
哀れみも冷ややかなるもただの眼ぞ楽しみて行く障害児らの遠足
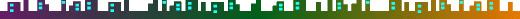
![]()