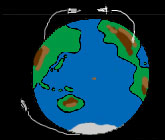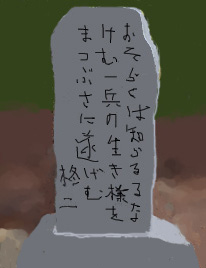|
高野略年譜 ・ 高野公彦秀歌その一 ・ 高野公彦秀歌その二 ・ 高野公彦秀歌その四 ・ 高野公彦秀歌その五 |
|
歌集「淡青」・昭和57年5月30日発行・雁書館・497首・33歳〜39歳 |
|
子ら眠り妻も眠ればゆたかなる暗闇の底灯ともして読む 歌集「淡青」
「子どもたちが眠り妻も眠れば、豊かなる暗闇の底に灯をともして読書をする」、という意味であろう。妻子のいない真夜中の暗闇の時間は自分だけの時間であり、好きなことができる時間である。私も真夜中、歌を詠む事が一番楽しい。こういう方は結構いるのではなかろうかと思う。
|
 |
|
卵もて食卓を打つ朝の音ひそやかに我はわがいのち継ぐ 歌集「淡青」
「卵で食卓のこんこんと打つ、朝のその音はひそやかであり、私はそれを食べて命を長らえている」、という意味である。我々は命で命を長らえているのであり、食べられる命に感謝すべきであろう。
|
|
エレベーターひらく則ち足もとにしづかに光る廊下来てをり 歌集「淡青」
「エレベーターが開くと直ぐに足元に静かに光っている廊下が来ていた」、という意味である。とても分かりやすい歌であり、誰もが経験することである。廊下が見えたではなく、来ていたという表現が詩的であり、静かに光っている廊下を歩きたくなるのである。
|
|
地下街は温感のなきひかり満ち目をみひらきて売らるる鸚哥 歌集「淡青」
「地下街は温かみのないひかりが満ちていて、目を見開きてインコが売れている」、という意味である。たしかに地下街のひかりはみんな同じような輝きであり、温かみはほとんど感じられない。そんな所に売られていたインコが作者は可哀想に感じられたのであろう。
|
|
雨一夜ふり足らひけり水辺の枝にあかるむ大かたつむり 歌集「淡青」
「雨が一晩降って水は十分満たされた。水辺の枝に水の反射光を浴びて明るく見える大蝸牛がいる」、という意味であろう。水辺は池か川であろうが、池の方がいいかも知れない。水を受けて蝸牛はいきいきとゆっくり動いているように見える。
|
|
牛を積む黒き車輌がゆふばえの鉄橋を連打してわたりゆく 歌集「淡青」
「牛を積んでいる黒い車輌が夕映えの鉄橋をゴトンガタンゴトンガタンと音を立てて渡りゆく」、という意味であろう。ただ単に車輌であると歌にならないが、牛を積んでいるということで情景がよく見え、歌になったように思う。
|
|
日なた雨すぎゆく堤おおばこの葉は土よりも早く濡れをり 歌集「淡青」
「日なた雨が過ぎてゆく堤に、オオバコの広い葉っぱは土よりも早く濡れている」、という意味である。日なた雨は天気なのに降っている雨のことである。観察の鋭い歌であり、作者は想像力だけでなく、観察力も優れた詩人である。
|
|
かたむきて虚空をわたる速雨(はやさめ)の白き脚みゆ時計塔の上に 歌集「淡青」
「傾いて大空を渡りゆく速い速度の白い雨脚が見える。時計塔の上に」、という意味である。速雨は夕立であろうか。斜めに通りゆく雨は見たことがある。速い雨は斜めに走りゆくのである。また「時計塔の上」という表現が距離も感じさせ、印象を鮮明にしているように思う。
|
 |
|
ふかぶかとあげひばり容れ淡青(たんじやう)の空は暗きまで光の器 歌集「淡青」
「深々と揚雲雀を淡青の広がる空は容れてくれる。その空は暗い所まで光の器である」、という意味であろう。青空が光の器という発見が詩的てあり、揚げ雲雀を容れることで、美しい情景が見えてくる。
|
 |
|
ねはん雪ふりいでてふりやまずけり空にて樹にて鳥は濡るるを 歌集「淡青」
「涅槃雪(涅槃会の前後に降る雪)が降り出して降りやまなくなった。空にて樹にて鳥は濡れているのだが」、という意味である。鳥の羽根は防水構造になっているが、限度を越えると中までしみ込んでしまうのであろう。その発見がおもしろい。
|
|
かたはらに公孫樹芽ぶけば街灯も春意を帯びてゆふべかがやく 歌集「淡青」
「傍らに公孫樹が芽吹けば、街灯も春めいて夕べ輝いている」、という意味である。春の息吹が公孫樹だけでなく、無機質の街灯の明るさにも感じられるということである。街灯にも春意があるという発見が詩的である。
|
|
あぢさゐの毬(まり)寄り合ひて色づけり鬼籠(ものこ)もらする如きしづけさ 歌集「淡青」
「紫陽花の丸くなった花が寄りそうて色づいている。鬼がその中に籠もっているような静けさだ」、紫陽花の色は赤と青が一般的だが、この場合、淡青が相応しいように思える。確かに紫陽花の中には何かがいるような雰囲気が感じられる。作者は鬼と感じたようである。
|
|
あした先づ飲む珈琲はくさぐさの思想より濃く胃の腑に沈む 歌集「淡青」
「朝、最初に飲むコーヒーは、様々な思想より深く濃く胃の中に沈んでいく」、という意味である。朝の一杯のコーヒーは格別ということであり、本当に様々な思想と比較している訳ではないのだろう。兎に角美味しいコーヒーは気分を和らげるのである。
|
 |
|
緑蔭に覚めしみどりごああといふはじめの言葉得てああと言ふ 歌集「淡青」
「緑蔭に目覚めた赤子が『ああ』と言う始めの言葉を得て、『ああ』と言った」、まず最初の言葉は母音の「ああ」なのだろう。言語学者が詠んだ歌のようである。言葉に鋭い感覚をもつ作者である。
|
|
泥あそびする子の上を種さげてタンポポの白い気球が通る 歌集「淡青」
泥遊びをする子供たちの上を、気球のようなタンポポの白い種がふわふわ通っていく」、という意味である。とても微笑ましい情景であり、私の好きな歌である。私もタンポポの歌を作ったことがあるが、気球という比喩は思いつかなかった。上質な詩人の発想である。
|
|
巨大なる無人区となり夜半のビルひえびえと自照灯を点せり 歌集「淡青」
「巨大な無人区となり、夜のビルは冷え冷えとして自照灯を点している」、という意味である。会社のビルの立ち並ぶ大都会は夜中ともなれば住む人もなく、無人の地区となる。人けのない地区に自照灯だけが輝いている。侘びしい光景である。
|
|
方位なき暗闇のなか寝返ればうゐのおくやまゆめ揺れにけり 歌集「淡青」
「方位感覚のない暗闇の中で、寝返ると夢も一緒に揺れたことだ」、という意味であろう。「うゐのおくやま」は、無常のこの世の中を道もなく越すに越されぬ深山にたとえた言葉であり、「色は匂へど」に始まる伊呂波歌の一節である。この場合、意味はたいしてないのであろう。ゆめにつながる枕詞のような働きをしているのではないであろうか。夢が体と一緒に揺れるという発想が素晴らしい。
|
|
ふるさとへわたる冬海おほいなる風の巣ありて風鳴りゐたり 歌集「淡青」
「故郷の四国へ渡る冬の海に、大いなる風の巣があって風が鳴り続れている」、という意味である。作者の故郷は四国の愛媛県であり、船から詠んだ歌であろう。「風の巣」という表現が斬新であり、詩人の発想である。
|
|
覚めしまま見てゐし夜の暗黒に灯を入れて我は此の世に戻りつ 歌集「淡青」
「目覚めながら目を開けて見ていた夜の暗闇に灯を付けて、私はこの世に戻って来た」、という意味である。暗黒にいる時、何を考えていたのだろうか。何を空想していたのだろうか。詩人の世界にいたと想像される。いい歌が出来たのではなかろうか。
|
|
海に出てなほ海中の谷をくだる河の尖端を寂しみ思ふ 歌集「淡青」
「海に出て、なおも海の中の谷をくだりゆく河の水の尖端を寂しく思う」、という意味である。河の水は海水とはすぐに交わらないで、海の中をなおも流れゆくという発見がとても素晴らしいと思う。でも何故河の尖端が寂しいのであろう。海水と交わろうとしない姿勢が寂しいのであろうか。
|
 |
|
骨太くわれ創られてふたふさの胸ある者に恋ひわたるなり 歌集「淡青」
「骨太く私は創られて、二房の胸ある者(女性)に恋してしまう」、という意味であろう。柔らかい女性の曲線に作者は魅入られているのであろう。もっとも男ならば大抵そうであるが。
|
 |
|
はるかなるひとつぶの日を燭(しょく)としてぎんやんま空にうかび澄みたり 歌集「淡青」
「遙かな彼方の太陽を燭台として、ギンヤンマが空に浮かび澄んで見える」、という意味であろう。太陽は夕日であろうか。燭台としての太陽のひかりが差し込み、美しい情景が想像できる。これも私の好きな歌の一つである。
|
 |
|
地下茶房にコーヒーを飲み昼休み動詞「おもふ」の中にわが棲む 歌集「淡青」
「地下室にある喫茶店でコーヒーを飲んでいる昼休み、動詞「思う」の中に私は存在している」、という意味である。つまり昼休みに喫茶店でコーヒーを飲みながら、何か考えているということであり、それはとても幸せな時間なのであろう。
|
|
歌集「雨月」・昭和63年7月1日発行・雁書館・579首・40歳〜44歳 |
|
病む母は見ずなりにけり海に光(て)る銀の朝浪、金の夕波 歌集「雨月」
病気の母は見なくなってしまった。海に光る銀色の朝方の波、金色に輝く夕方の波」、という意味である。「銀の朝浪、金の夕波」という表現がリズム感があってよいと思う。歌の意味を重んじる方が多いが、調べの良い歌は口ずさみやすく、記憶にも残りやすいと思う。名歌は調べが大抵良いようである。
|
|
妻子率(ゐ)て公孫樹のもみぢ仰ぐかな過去世・来世にこの妻子無く 歌集「雨月」
「妻子と一緒にイチョウのもみじを仰いでいる。私の過去の世にも未来の世にもこの妻子はいないのだなあ」、という意味である。人間は何度も生まれかわりするという思想を基盤としている。現世は過去世にも来世にも関連していないらしい。寂しく、かつわくわくする世界観ではある。
|
 |
|
死者、事故車運び去られて乾く路迅(はや)しするどし都市の自浄は 歌集「雨月」
「死者や事故車はすぐに運び去られて道路は、直ぐに乾いてしまう。都市の自浄作用は、速くかつ鋭い」、という意味である。交通事故は速く処理しなければ道路の渋滞が激しくなってしまうのである。都市は抒情では動かないのである。処理的事務的ではある。
|
|
夜ざくらを見つつ思ほゆ人の世に暗くただ一つある〈非常口〉 歌集「雨月」
「夜桜を見ながら思う。人の世に暗くただ一つある、非常口というものは」、という意味であろう。映画館など、大抵非常口は暗がり見られものである。逃げ口であるが、大抵の人は開けることはないであろう。これを使用する時は、何か大変なことがあった時である。夜桜から非常口への発想が詩人の感性である。
|
 |
|
死なむとする母のいのちを死なしめず手厚く冷厳なりき現代医療は 歌集「雨月」
「病気で死のうとしている母の命を死なないようにしている、手厚く冷静でおごそかであることだ。現代医療というは」、という意味である。確かに昔ならとうに亡くなっている患者でも現代医学は生きながらえるように治療してくれている。素晴らしいことだと思う反面、無理矢理に生かし続けても仕方ないのではないかという考えの方もたくさんいるように思う。難しい問題ではある。
|
|
林檎より剥かれゆく皮ゆらゆらと女体に沿ひて降下する見ゆ 歌集「雨月」
「林檎より剥かれてゆく皮がゆらゆらと女性の体に沿ひながら下がってゆくのが見える」、という意味である。身近な女性なのであろう。裸の女性を想像してしまうのは私だけであろうか。
|
 |
|
巨大なる〈核の倉庫〉となりはてし天体一つ宇宙にうかぶ 歌集「雨月」
「巨大な核兵器の倉庫となり果てた地球という天体が宇宙に浮かんでいる」、という意味である。この大宇宙に核兵器の倉庫としての惑星がいくつ存在しているのだろう。ひょっとして地球だけではないのかと思う。いつ破裂するか分からない惑星である。
|
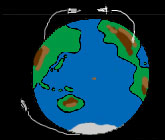 |
|
水べりのくるみを照らし我をてらし水はやはらかき女人のひかり 歌集「雨月」
「水辺の枝の胡桃を照らし、我を照らし、水の反射光は女のもつ柔らかい光のようだ」、という意味であろう。水のゆらめく光は柔らかく感じられる。それが女性的ということであろう。詩人の主観的発想であり、そういわれればそんなものかも知れない。
|
|
歌集「水行」・平成3年8月15日発行・雁書館・708首・45歳〜48歳 |
|
〈歌阿修羅・酒阿修羅〉より〈歌菩薩・病菩薩〉となりて逝きませり 歌集「水行」
〈歌の世界で苦しむ阿修羅・酒を飲みすぎ苦しむ阿修羅〉そういう者から〈歌を楽しむ菩薩・病に苦しむ菩薩〉となってお亡くなりになった」、という意味であろう。親しい歌人のことを詠んだのであろう。その方は日々歌つくりに苦しみ、また酒に溺れていたが、最後は歌を楽しみ、かつ病気となってしまったのである。歌は病を一時忘れさせてくれるのかも知れない。
|
|
究極の人生は? と問はれて。
「歌を詠み秀歌五、六首。晩年に世を捨てて伝詳(つまびら)かならず」 歌集「水行」
究極の人生は? と人に訊かれて、このように答えた。「歌を詠み、秀歌を五、六首残し、晩年に世捨て人となり、行方不明になった人だ」、という意味である。歌人の鏡のような生き方である。家庭も妻子もいらない、歌さえあればよいという人生が理想としては好きなのであろう。しかし実際はそういう訳にはいかないのである。
|
 |
|
湯どうふよ わが身は酔つてはるかなる美女(びんぢよう)恋し なあ湯どうふよ 歌集「水行」
「湯どうふよ わが身は酔って遙かなる美女が恋しい なあ湯どうふよ」、という意味である。この場に奥さんは居ないのである。私もこういう感覚をもつことがあるが、なかなか歌にはできないのである。妻に知れたらまずいと思うからである。
|
 |
|
藤の花咲けりこの世はつねにつねに誰か逝きたるあとの空間 歌集「水行」
「藤の花が咲いている。この世の中は常に常に誰かが死んだ後の空間である」、という意味である。確かに誰かが何処かで死んでいる。その通りであるが、誰かが生まれた後の空間ともいえる。見方によっては違う面が見えるということを暗示している歌ではある。
|
|
原子炉のとろ火で焚いたももいろの電気、わが家のテレビをともす 歌集「水行」
「原子炉の炎で造った桃色の電気が、わが家のテレビを灯している」、という意味である。原子力発電を否定しているのであろうか。その発電に頼ってきた今までの歴史がある。しかしあの大震災でその発電を否定する人も多くなってきた。「ももいろの電気」という表現が詩的である。
|
|
宮柊二は歌の中に在り歌碑といふ大きな石の中には坐(ま)さず 歌集「水行」
「わが師、宮柊二の心は歌の中に存在するのであり、歌碑という大きな石碑の中にあるわけではない」、という意味である。歌という表現の中に柊二の思いや願い、主張はあるのだろう。だがイスラム教徒ではないので、日本人は石碑を建てたくなるのだと思われる。
|
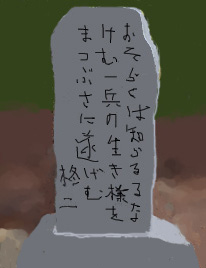 |
|
内なる〈死〉わがししむらを軽打して頭髪すこしづつ白くなる 歌集「水行」
「体の中の細胞の死を意識して、私の肉体を軽く叩きながら、頭髪が少しずつ白くなっていく」、という意味であろう。老いるということは少しずつ死んでいくということである。体の中から少しずつ少しずつ死が迫って来るのである。
|
|
二十代だったころ。
能見つつ我はねむりき黄金の風のほとりのねむりなりけり 歌集「水行」
「能を見ながら(二十代の頃の)私は眠ってしまった。黄金の風のような能の素晴らしさが理解できず、その風のほとりで眠ってしまった」、という意味であろう。若者が能を理解できないのは何も不思議なことではない。その奥深さが理解できるには年齢を重ねる必要があるのではないかと思う。
|
|
その人は伊予の人にて句と歌を革めながら都で死せり 歌集「水行」
「その人(正岡子規)は、(四国の)伊予の人にて、俳句と短歌の改革を推し進めながら東京で亡くなった」、という意味である。正岡子規が好きだったようである。私も好きである。
|
 |
|
アル中で妻と別れて島にわたり黙つて死んだ放哉が好きだ 歌集「水行」
「アル中で妻と別れて島(小豆島)に渡り、(寺男となって)黙って死んだ放哉が好きだ」、という意味である。尾崎放哉は自由律の俳人であり、東大は出ているが、性格破綻者であり、酒に溺れ、妻に逃げられ、まともな人間からは嫌われていた方である。代表作は「咳をしても一人」である。自業自得な一生であった。こういう生き方に憧れていたということが不思議であり、高野短歌を研究する上で貴重な情報である。
|
 |
|
耳飾りに耳を噛ませて出(い)で歩くやはらかき不思議の生きもの 歌集「水行」
「耳飾りに耳を噛ませて出歩く人間は、柔らかく不思議な生き物である」、という意味である。作者は耳飾りをやや否定的に見ているようである。そういう時代だったのであろう。今ではおそらく当たり前すぎて、不思議な生き物とは感じないと思われる。
|
|
にんげんの水行(すいかう)の跡すべて消し海はしづけきひかりの平 歌集「水行」
「人間の水に関する行いの全てを消し去り、海は静かで平らな光となって見える」、という意味である。放射能汚染を含め、人間は水を汚して海に流すが、海はそれを静かに受けとめ、一枚の光の面となっているようである。
|
 |
|
作成中by小山 |